Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
新藤 浩之*; 緑川 正彦*; 佐藤 洋平*; 久保山 智司*; 平尾 敏雄; 大島 武
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 5, 2008/11
活性層が薄くイオン入射に伴い発生する電子・正孔対の総量を抑制することができるため、耐放射線性半導体素子として期待される0.15 mFD-SOI(Fully Depleted Silicon on Insulator)上に作製した、FPGA(Field Programmable Gate Array)要素回路の放射線耐性評価をAr 150MeV(LET: 15.1/(mg/cm
mFD-SOI(Fully Depleted Silicon on Insulator)上に作製した、FPGA(Field Programmable Gate Array)要素回路の放射線耐性評価をAr 150MeV(LET: 15.1/(mg/cm )), Kr 322MeV(LET: 37.9/(mg/cm
)), Kr 322MeV(LET: 37.9/(mg/cm )), Xe 454MeV(LET: 60.6/(mg/cm
)), Xe 454MeV(LET: 60.6/(mg/cm ))を用いて実施した。その結果、FPGAを構成する基本回路の一つであるConfiguration bitのSEUの発生要因として、OFF状態のトランジスタが一つだけ反転することでSETが発生するSTG(Single transient gate)モードと高LET粒子が冗長トランジスタを同時に駆動してしまうDH(Duble Hit)モードの2種類があることがわかった。さらにSEU反転断面積とLETとの関係において、STGモードではLETが40MeV/(mg/cm
))を用いて実施した。その結果、FPGAを構成する基本回路の一つであるConfiguration bitのSEUの発生要因として、OFF状態のトランジスタが一つだけ反転することでSETが発生するSTG(Single transient gate)モードと高LET粒子が冗長トランジスタを同時に駆動してしまうDH(Duble Hit)モードの2種類があることがわかった。さらにSEU反転断面積とLETとの関係において、STGモードではLETが40MeV/(mg/cm )以下でエラー発生が観測されないこと、一方DHモードではLETが60MeV/(mg/cm
)以下でエラー発生が観測されないこと、一方DHモードではLETが60MeV/(mg/cm )以下でエラー発生が観測されない結果を得た。この結果は、従来のバルクシリコンで得られている閾値LET(LET:15.1/(mg/cm
)以下でエラー発生が観測されない結果を得た。この結果は、従来のバルクシリコンで得られている閾値LET(LET:15.1/(mg/cm ))と比較して2.6
))と比較して2.6 4.5倍も耐性が向上されている。さらにこの結果から、FPGA回路に対する耐SEUを改善するために必要なパラメータの取得ができた。
4.5倍も耐性が向上されている。さらにこの結果から、FPGA回路に対する耐SEUを改善するために必要なパラメータの取得ができた。
平尾 敏雄; 小野田 忍; 高橋 芳浩*; 大島 武
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 6, 2008/11
酸化膜を介した照射誘起電流の発生機構解明を目的に、MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)へ重イオン照射を実施した。試料はバルクシリコンAlゲートp-及びn-channel MOSFET(酸化膜厚=40nm, ゲート幅=100mm, ゲート長=300 m)を用い、15MeV酸素イオンを照射した。イオン照射誘起電流をTIBIC(Transient Ion Beam Induced Current)測定装置を用いて評価したところ、MOSキャパシタでは、印加電圧の増加に伴い、過渡電流のピーク値が直線的に増加することがわかった。さらに、照射後1
m)を用い、15MeV酸素イオンを照射した。イオン照射誘起電流をTIBIC(Transient Ion Beam Induced Current)測定装置を用いて評価したところ、MOSキャパシタでは、印加電圧の増加に伴い、過渡電流のピーク値が直線的に増加することがわかった。さらに、照射後1 2ns程度に酸化膜に印加した電界方向の鋭い電流ピークが、その後反対方向に小さな電流がそれぞれ観測された。結果に対し、酸化膜を完全絶縁と仮定して発生した誘起電流をキャリア濃度及び移動度を主パラメータとして数値シミュレーションを行った結果、MOSFETのゲート領域に重イオンを照射した際に観測される照射後1
2ns程度に酸化膜に印加した電界方向の鋭い電流ピークが、その後反対方向に小さな電流がそれぞれ観測された。結果に対し、酸化膜を完全絶縁と仮定して発生した誘起電流をキャリア濃度及び移動度を主パラメータとして数値シミュレーションを行った結果、MOSFETのゲート領域に重イオンを照射した際に観測される照射後1 2ns程度経過後の鋭いピークとその後の反対方向のブロードな電流ピークをシミュレーションにより得ることに成功し、実験結果との良い一致を図ることができた。
2ns程度経過後の鋭いピークとその後の反対方向のブロードな電流ピークをシミュレーションにより得ることに成功し、実験結果との良い一致を図ることができた。
須郷 由美; 田口 光正; 永石 隆二; 佐々木 祐二; 広田 耕一; 木村 貴海
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 161, 2008/11
マイナーアクチノイド分離用抽出剤TODGAへの 線による放射線分解特性を調べる目的で、TODGAを溶解したドデカン溶液に、高崎量子応用研究所イオン照射研究施設のAVFサイクロトロンから生じるHeイオンビームを深度制御種子照射装置(HY1)を用いて垂直方向にスキャン照射した。照射後試料をガスクロマトグラフ質量分析装置で分析し、分解生成物の種類や収量を
線による放射線分解特性を調べる目的で、TODGAを溶解したドデカン溶液に、高崎量子応用研究所イオン照射研究施設のAVFサイクロトロンから生じるHeイオンビームを深度制御種子照射装置(HY1)を用いて垂直方向にスキャン照射した。照射後試料をガスクロマトグラフ質量分析装置で分析し、分解生成物の種類や収量を 線の照射実験の結果と比較した。その結果、
線の照射実験の結果と比較した。その結果、 線照射に比べHeイオンの照射では吸収線量の増加に伴うTODGAの分解率の変化が小さく、
線照射に比べHeイオンの照射では吸収線量の増加に伴うTODGAの分解率の変化が小さく、 線照射ではドデカン中のTODGAの分解が抑えられることがわかった。これは、LETの高い
線照射ではドデカン中のTODGAの分解が抑えられることがわかった。これは、LETの高い 線の照射では、局所的に活性種が生成するため、溶媒による間接効果の影響が小さくなるためであると考えられる。
線の照射では、局所的に活性種が生成するため、溶媒による間接効果の影響が小さくなるためであると考えられる。
飯塚 正英*; 吉原 亮平; 長谷 純宏
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 65, 2008/11
オステオスペルマムは、キク科の多年草で開花時期が長く、鉢物や花壇材料として生産が増加している。本研究では、イオンビーム照射で得られたオステオスペルマムの白色花弁変異体OM7に、もう一度イオンビームを照射して、完全な表裏白色花弁を誘導することを試みた。現在までに、再照射試料から1582個体が得られ、このうち花弁の色や形の変化を指標にして22個体を選別した。再照射によって、1回目の照射では得られなかった紫色の花弁を持つ個体や多弁変異個体が得られた。このことから、再照射は、色素合成や形態変異の経路に付加的な変異を与えていることが示唆された。花弁の色変化については明橙色になったものも得られている。また、オステオスペルマムの花弁は表と裏で色彩が異なるが、裏側が淡黄色に変化したものが見られた。現在、この裏側の花弁の色が薄くなった2系統について、さらなる解析を進めている。
岡村 正愛*; 清水 明*; 大西 昇*; 長谷 純宏; 吉原 亮平; 鳴海 一成
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 62, 2008/11
本課題では、有用形質転換体へイオンビームを応用するシステムを開発することにより、さまざまな花色や形の品種をシリーズ化する手法を確立し、イオンビーム高度利用技術の開発に資することを目的とする。照射材料としては、分裂酵母由来の2本鎖RNA特異的RNA分解酵素( )を導入することでキク発育阻害ウイロイド及びトマト黄化壊疽ウイルスに耐性を獲得した形質転換キクを用いた。これまでに炭素イオンビームの照射試験を実施し、順化,温室での栽培後、花色と花姿について調査した。照射によって得られた計832の個体について開花試験を行い、薄桃,濃桃,サーモン,白色,黄色などの花色変化を誘導できることを明らかにした。これらの結果から、この方法は、個々の遺伝子導入による従来法に比べて、低コストで高い品質の鑑賞植物の開発に有効であると考えられた。
)を導入することでキク発育阻害ウイロイド及びトマト黄化壊疽ウイルスに耐性を獲得した形質転換キクを用いた。これまでに炭素イオンビームの照射試験を実施し、順化,温室での栽培後、花色と花姿について調査した。照射によって得られた計832の個体について開花試験を行い、薄桃,濃桃,サーモン,白色,黄色などの花色変化を誘導できることを明らかにした。これらの結果から、この方法は、個々の遺伝子導入による従来法に比べて、低コストで高い品質の鑑賞植物の開発に有効であると考えられた。
竹之下 佳久*; 遠嶋 太志*; 西 裕之*; 白尾 吏*; 長谷 健*; 大江 正和*; 長谷 純宏; 鳴海 一成
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 66, 2008/11
沖縄県久米島地域及び鹿児島県奄美地域を普及対象として育成されたサトウキビ品種「Ni17」は株出し適性が高く、耐風性も強い。しかし、葉鞘部に着生する毛群が粗剛であるため、収穫や栽苗等の作業に障害をきたしている。そこで、イオンビーム照射による突然変異誘発により毛群の少ない優良系統の育成を試みた。幼苗検定により初期選抜した188個体について、ほ場での毛群及び生育調査を行い、毛群が少なく生育の良好な有望個体30個体を選抜し、南西諸島の徳之島現地圃場の系統選抜試験に供試した。2年間の特性調査の結果、有望な系統「KB04-25」を選抜した。「KB04-25」は春植栽培において、毛群の発生が「Ni17」に比べて少なくなっており、収量面においては、茎径が細くなり1茎重は18%減少したものの、茎長が15cm長くなり、茎数が52%増加したために収量は19%増加した。茎の細茎化については風折抵抗性が低下することが想定されるため、今後検討が必要である。


 hort (cv. White Aga)
hort (cv. White Aga)近藤 正剛*; 小池 洋介*; 奥原 宏之*; 小田 正之*; 長谷 純宏; 吉原 亮平; 小林 仁*
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 67, 2008/11
ユリは、我が国における切り花の粗生産額でキク,バラについて第3位の地位を占め、球根出荷量でもチューリップに次ぐ第2位であり、園芸植物として重要な花卉である。新潟県農業総合研究所では、アグロバクテリウム法によるユリの形質転換系を確立し、花色改変による新品種の作出に取り組んでいる。遺伝子組み換えにより作出した植物を普及するためには、花粉の飛散による環境への遺伝子拡散を管理しなくてはならないため、雄性不稔であることが望ましい。そこで、ユリの不稔化を目的として、組織培養系とイオンビーム照射を組合せた突然変異育種による共同研究を進めている。テッポウユリ(品種:ホワイト阿賀)のカルスに、100MeVのヘリウムイオンビームを0から2Gy照射したものを育成し、葯の形態異常によって花粉が少ない10個体を選抜した。このうち、0.8Gy照射したものから得られた変異体は、葯が捻れて花粉が少ないほかは、ホワイト阿賀と同様の形質を示した。今後、この変異体について花粉の稔性を調査する予定である。

松尾 陽一郎*; 西嶋 茂宏*; 長谷 純宏; 坂本 綾子; 鳴海 一成; 清水 喜久雄*
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 60, 2008/11
本研究は、真核生物のモデル生物である出芽酵母 を用いて、イオンビームで生じる突然変異誘発の分子機構を解明することを目的とする。今回、野生株とDNAグリコシラーゼ活性の欠損によって8オキソデオキシグアニン(8-oxodG)を除去できない
を用いて、イオンビームで生じる突然変異誘発の分子機構を解明することを目的とする。今回、野生株とDNAグリコシラーゼ活性の欠損によって8オキソデオキシグアニン(8-oxodG)を除去できない 変異株を用いて、5-フルオロオロト酸耐性を指標として取得した
変異株を用いて、5-フルオロオロト酸耐性を指標として取得した 変異体を解析し、高LET炭素イオンビームによって生じる8-oxodGの突然変異誘発性を調べた。
変異体を解析し、高LET炭素イオンビームによって生じる8-oxodGの突然変異誘発性を調べた。 変異株の100Gy照射での
変異株の100Gy照射での 変異の出現頻度は野生株の2倍であった。野生株では
変異の出現頻度は野生株の2倍であった。野生株では 遺伝子に起こった突然変異のうちG
遺伝子に起こった突然変異のうちG T塩基置換が全体の41%を占めていたのに対して、
T塩基置換が全体の41%を占めていたのに対して、 変異株ではG
変異株ではG T塩基置換が全体の70%を占めていた。野生株では塩基置換のほかに挿入変異や欠損変異が認められたのに対して、
T塩基置換が全体の70%を占めていた。野生株では塩基置換のほかに挿入変異や欠損変異が認められたのに対して、 変異株では挿入変異や欠損変異が認められなかった。
変異株では挿入変異や欠損変異が認められなかった。
茅根 俊平*; 徳弘 晃二*; 中坪 弘一*; 長谷 純宏; 鳴海 一成
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 68, 2008/11
本研究ではデルフィニウム及びスターチスシヌアータの花色などにおいて特徴のある変異体獲得を目的としてイオンビーム照射を行った。カネコ種苗育成のデルフィニウム「7P」の培養体の葉身、及びスターチスシヌアータ「P08」の花穂の節をシャーレに置床し、約1週間後に炭素イオンビームを照射した。デルフィニウムでは、シュートの分化数が照射区で減少した。適正線量は0.5 1.0Gyと推測された。スターチスシヌアータでは、線量による生存率の差は小さかったが、線量が強くなるにつれ水浸状化及びシュートの分化がみられない節が多くみられた。適正線量は1.0Gy付近であると推測された。デルフィニウムでは再分化した174個体をポットへ移植し、また、スターチスシヌアータでは441個体を順化し、花色等の特性について調査する予定である。
1.0Gyと推測された。スターチスシヌアータでは、線量による生存率の差は小さかったが、線量が強くなるにつれ水浸状化及びシュートの分化がみられない節が多くみられた。適正線量は1.0Gy付近であると推測された。デルフィニウムでは再分化した174個体をポットへ移植し、また、スターチスシヌアータでは441個体を順化し、花色等の特性について調査する予定である。
古谷 規行*; 松村 篤*; 長谷 純宏; 吉原 亮平; 鳴海 一成
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 69, 2008/11
盆コギクは、仏花として出荷期が決まっているが、天候による開花変動が大きく、産地では危険分散のために多くの品種が作付けされている。こうした中、京都府では開花変動が少なく花色が赤紫色の「H13」を育成した。しかし、盆コギクとしては赤・白・黄の3色セットが望まれている。そこで、イオンビームを用いた突然変異育種法に取り組むこととした。「H13」からは花色が暗赤色,朱色,ピンク及び赤白混合色の変異体を得ることができた。また花弁が肥大した個体及び八重咲きの個体を選抜した。さらに「H13」の草型の改善点として指摘されていた、ひし形咲きからT字咲きの個体を選抜した。今後、花色や草型等の特性を調べ、二次選抜を行う予定である。また、さらに大きな変異を誘発させる目的で、一次選抜株に再度イオンビームを照射した。現在、育成した株をガラス温室内で栽培中であり今後、開花調査を実施する予定である。
小林 伸雄*; 田崎 啓介*; 加納 さやか*; 坂本 咲子*; 中務 明*; 長谷 純宏; 鳴海 一成
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 70, 2008/11
本研究では、花色及び花姿の突然変異を誘導するために、ツツジ4品種(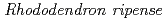 ,
, 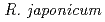 ,
,  及び
及び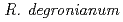 var.
var.  )の種子に220MeV炭素イオンビームを0から50Gy照射した。
)の種子に220MeV炭素イオンビームを0から50Gy照射した。 と
と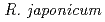 については20Gy照射区まで生存し、また、
については20Gy照射区まで生存し、また、 と
と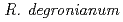 var.
var.  は30Gy照射区まで生存できた。発芽率は非照射区で最も高かったが、生存率は非照射区よりも低線量照射区の方が高かった。これは、イオンビーム照射による刺激効果によるものであろう。斑入りの葉を持つものが幾つかの苗木で観察された。矮性や発育阻害も観察された。
は30Gy照射区まで生存できた。発芽率は非照射区で最も高かったが、生存率は非照射区よりも低線量照射区の方が高かった。これは、イオンビーム照射による刺激効果によるものであろう。斑入りの葉を持つものが幾つかの苗木で観察された。矮性や発育阻害も観察された。
金澤 章*; 阿部 純*; 長谷 純宏; 鳴海 一成
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 71, 2008/11
大豆は、食糧,油,飼料として重要な穀物であるが、現存する大豆の変異系統は限られており、育種並びに遺伝解析を行うための制約となっている。本研究では、イオンビーム照射が大豆の突然変異体を作出するのに有効かどうかを調べることを目的とした。大豆乾燥種子に0.2から25Gyの320MeV炭素イオンを照射後、播種し、温室で3週間栽培した。5Gy以上の線量で植物生育に影響が見られ、大豆の突然変異誘導に最適な線量は2から5Gyであると考えられた。2Gy及び5Gy照射区では、初生葉中心部での狭窄や不定期な葉柄発生が顕著に認められた。照射種子を圃場で1か月半栽培し、草高を調査したところ、照射線量に依存して草高の低下が認められた。生存率も照射線量に依存して低下した。2.5Gy照射区1,400個体のM2種子を収穫済みであるので、今後、変異体を選抜するための後代を栽培する予定である。
 C
C ビームと
ビームと 線の影響
線の影響津呂 正人*; 岩田 千鶴*; 片岡 利栄*; 吉原 亮平; 長谷 純宏
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 72, 2008/11
ラバンジンは真正ラベンダーとスパイクラベンダーとの種間雑種であり、雑種強勢により精油成分の生産性が両親種より高いことが知られている。一方、カンファーあるいはボルネオール等の香質低下成分も増加していることから、これら成分の生産が抑制された突然変異体の作出が求められている。本研究では、培養単離細胞へ種々の線量の 線を照射し、培養細胞の増殖に及ぼす影響を調査するとともに、
線を照射し、培養細胞の増殖に及ぼす影響を調査するとともに、 C
C ビーム及び
ビーム及び 線照射細胞からのシュート再生を試みた。炭素ビームを照射したとき、
線照射細胞からのシュート再生を試みた。炭素ビームを照射したとき、 線と比較して低い線量で増殖が抑制されており、細胞の増殖に及ぼす線量効果が両者で著しく異なることが明らかとなった。増殖したカルスをシュート誘導培地に移植して培養したとき、一部のカルスからシュートの形成が認められた。カルスの増殖誘導と同様にシュート形成においても炭素ビームと
線と比較して低い線量で増殖が抑制されており、細胞の増殖に及ぼす線量効果が両者で著しく異なることが明らかとなった。増殖したカルスをシュート誘導培地に移植して培養したとき、一部のカルスからシュートの形成が認められた。カルスの増殖誘導と同様にシュート形成においても炭素ビームと 線照射区において反応が異なった。現在、両照射区で得られたシュートの発根・馴化を行っている。
線照射区において反応が異なった。現在、両照射区で得られたシュートの発根・馴化を行っている。
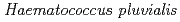 からのアスタキサンチン高生産変異株のスクリーニング
からのアスタキサンチン高生産変異株のスクリーニング柿薗 俊英*; 大道 大輔*; 吉原 亮平; 長谷 純宏; 鳴海 一成
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 73, 2008/11
高度に抗酸化力を有するアスタキサンチン(ASX)は、ほとんどの種類の甲殻類,サーモンの肉色,タイの体表皮など海洋生物に広く分布するケトカロテノイドである。微細緑藻 の栄養細胞のカロテノイド色素は少量であるが、栄養条件の悪化とともにシスト細胞と呼ばれる胞子嚢細胞へ形態変化し、アスタキサンチンを細胞重量比で2から3%の著量に生成する。そこで、本緑藻が太陽光によらずに暗所で酢酸を炭素源に従属栄養的に増殖し、ASX生成を行いうることに着目し、その大規模生産の可能性を検討している。イオンビーム変異導入法を用いて、酢酸耐性変異株等を広範囲にスクリーニング・単離することを目的に、イオンビーム強度を種々に変化させて変異細胞調製を行い、変異株を種々の酢酸濃度からなる液体培地又は寒天培地に塗布し、案諸条件で継代培養を検討してきた。その結果、寒天培地の方がシスト細胞に形態変化しやすいことがわかった。
の栄養細胞のカロテノイド色素は少量であるが、栄養条件の悪化とともにシスト細胞と呼ばれる胞子嚢細胞へ形態変化し、アスタキサンチンを細胞重量比で2から3%の著量に生成する。そこで、本緑藻が太陽光によらずに暗所で酢酸を炭素源に従属栄養的に増殖し、ASX生成を行いうることに着目し、その大規模生産の可能性を検討している。イオンビーム変異導入法を用いて、酢酸耐性変異株等を広範囲にスクリーニング・単離することを目的に、イオンビーム強度を種々に変化させて変異細胞調製を行い、変異株を種々の酢酸濃度からなる液体培地又は寒天培地に塗布し、案諸条件で継代培養を検討してきた。その結果、寒天培地の方がシスト細胞に形態変化しやすいことがわかった。
松尾 洋一*; 長谷 純宏; 吉原 亮平; 鳴海 一成
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 74, 2008/11
ユズは樹体に長いトゲが発生するため、栽培管理上障害となっている。さらに、トゲによる刺し傷はキズ果や腐敗果の発生など果実の商品性を低下させる。そこで、ユズ実生の胚軸断面からシュートを再生させる培養系に重イオンビームを照射し、トゲ消失変異体の作出を試みた。2線量区で再生シュートを育成し、トゲ消失変異候補個体を作出した。さらに、前回育成した候補個体の果実品質を確認するため、12年生温州ミカン(大津4号)に高接ぎを実施した。さらに、県内カンキツ生産の主力品目である温州ミカンの有望系統を作出するため、照射条件や線量の検討に着手した。また、今後はカンキツ由来の機能性成分として注目されているポリメトキシフラボン等の機能性成分を高含有した品種を育成するために、照射個体の成分分析を実施していく。
浅見 逸夫*; 福田 至朗*; 黒柳 悟*; 大竹 良知*; 長谷 純宏; 吉原 亮平; 鳴海 一成
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 76, 2008/11
日本のイチジク産地で栽培されている品種は、ほとんどが「桝井ドーフィン」である。また、日本での栽培に適したフィッグ型イチジク品種はほとんど雌花しか着生しないことから他品種との交雑育種は困難であり、これまで遺伝子資源の拡大はされてこなかった。そこで本研究では、イオンビームを利用して高品質で特徴ある新品種開発につながる遺伝子資源を創成することを目的とした。炭素イオンビームを2.5Gyから20Gyまで段階照射したところ、10Gyを越えると生存率が低下した。また、10mm以上伸長する腋芽の割合、伸長した腋芽の茎長及び重量は5Gyから7.5Gy照射で非照射区の平均値に対して50%程度にまで低下した。腋芽が生存しても伸長しなければ選抜に用いることができないことから、10mm以上伸長する腋芽がわずかに残る10Gyが上限と考えられた。
千葉 直樹*; 荒川 梢*; 中村 茂雄*; 岩崎 泰永*; 吉原 亮平; 長谷 純宏; 鳴海 一成
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 78, 2008/11
イチゴの栽培は、促成品種の導入と施設栽培技術の発達により収穫期間が前進化し、かつ長期化している。本研究ではイチゴ品種の変異拡大を目的として、イチゴに対するイオンビームの適正線量を測定するとともに、イオンビーム照射が花房の発生時期に及ぼす影響を調査した。イチゴ品種は「もういっこ」を用いた。無菌培養で増殖した腋芽を含む切片に対してヘリウムイオンあるいは炭素イオンを照射した。イオンビームに対する再生率の線量反応を調査した結果、ヘリウムでは16Gy、炭素では32Gyより高い線量で再生率が低下した。イチゴの再生率に影響がない炭素イオンの8Gyと16Gy照射処理区から、合計286株のM1世代を得た。無処理区で最も早い着蕾日は1月4日であった。この日より早く着蕾した8Gy処理12株と16Gy処理8株の合計20株を選抜株とした。今後、収穫期間における花房発生の連続性や収量・品質等について継続的に調査を行う。
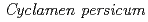

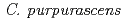 )のイオンビーム照射による変異誘導
)のイオンビーム照射による変異誘導近藤 恵美子*; 長谷 純宏; 鳴海 一成; 石坂 宏*
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 79, 2008/11
シクラメンの栽培種と芳香性野生種の種間交雑により雑種を育成し、その染色体倍加により複二倍体の芳香シクラメンを育成した。しかし、芳香シクラメンの花は色,形,大きさの変化が乏しいため、形質の多様化が求められている。そこで、イオンビーム照射と組織培養を利用した突然変異育種による変異の拡大を検討した。種子を無菌的に播種し暗黒下で培養することにより発生させた黄化葉柄,葯培養から作出した半数体を暗黒下で培養することにより発生させた黄化葉柄,開花個体から着色する前に採取した未熟な花弁を供試した。花弁には220MeV炭素イオンを、黄化葉柄には320MeV炭素イオンをそれぞれ0から50Gyの範囲で照射し、その後、培養を行った。イオンビーム照射により花弁に現れた変異は、花色の濃淡,花弁の矮小化,花弁周囲の鋸歯,斑入りなどであったが、花弁以外にも葉の斑入りなどの変異が現れた。今後、花の色素,香気成分に関する変異の解析及び世代更新による有望な変異形質の固定をとおして品種育成を進める予定である。
辻 誠一*; 宮本 守*; 長谷 純宏; 鳴海 一成
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 75, 2008/11
宿根かすみそう・りんどうは切花用として栽培・出荷されている重要な花き作物である。本研究は、これらの花き作物について、イオンビーム照射による新たな有用変異の誘発の可能性についての知見を得ることを目的とする。宿根かすみそう「ブリストルフェアリー」及び類縁関係を持つ5品種について、2回に渡り4Gyの炭素イオンビーム照射を実施した。照射試験で833の再生個体が得られ、2007年11月からハウス隔離栽培により変異の有無の調査を実施してきている。現在まで、葉が幅広で肉厚である個体を含む38の変異個体を一次選抜した。変異の内訳としては、早晩性5%,茎葉の形態63%,花器の形態31%であった。りんどう(在来系統)については、2008年2月までに、照射当代95個体から自殖種子を得た。現在、次世代種子が得られた系統について播種・育苗を行っており、今秋、変異体の選抜を行う予定である。
高橋 芳浩*; 府金 賢*; 今川 良*; 大脇 章弘*; 平尾 敏雄; 小野田 忍; 大島 武
JAEA-Review 2008-055, JAEA Takasaki Annual Report 2007, P. 7, 2008/11
MOS(Metal Oxide Semiconductor)構造の重イオン照射誘起ゲート電流の 線照射による変化について評価を行った。試料はp形及びn形バルクSi基板上の、酸化膜厚100nm,Alゲート電極直径100
線照射による変化について評価を行った。試料はp形及びn形バルクSi基板上の、酸化膜厚100nm,Alゲート電極直径100 mのMOSキャパシタとした。
mのMOSキャパシタとした。 線照射は吸収線量率6.3kGy(SiO
線照射は吸収線量率6.3kGy(SiO )/hで1時間行った。照射前後のイオン照射誘起ゲート過渡電流の測定は、酸素イオン(15MeV)を用いたTIBIC(Transient Ion Beam Induced Current)評価システムにより行った。また、
)/hで1時間行った。照射前後のイオン照射誘起ゲート過渡電流の測定は、酸素イオン(15MeV)を用いたTIBIC(Transient Ion Beam Induced Current)評価システムにより行った。また、 線照射前後において容量-電圧特性及びリーク電流特性の測定を行った。その結果、
線照射前後において容量-電圧特性及びリーク電流特性の測定を行った。その結果、 線照射後、同一電圧印加時のゲート過渡電流ピーク値は、p-MOSにおいて増加し、n-MOSでは減少した。さらに容量-電圧特性で生じた変化を正電荷捕獲密度を反映したミッドギャップ電圧のシフト量で評価し、そのシフト量分、ゲート印加電圧値をシフトさせた結果、照射前後でのピーク値はよく一致することが判明し、ピークのシフトが正の固定電荷発生によることが明らかとなった。
線照射後、同一電圧印加時のゲート過渡電流ピーク値は、p-MOSにおいて増加し、n-MOSでは減少した。さらに容量-電圧特性で生じた変化を正電荷捕獲密度を反映したミッドギャップ電圧のシフト量で評価し、そのシフト量分、ゲート印加電圧値をシフトさせた結果、照射前後でのピーク値はよく一致することが判明し、ピークのシフトが正の固定電荷発生によることが明らかとなった。