Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
鈴木 崇史; 乙坂 重嘉; 桑原 潤; 川村 英之; 小林 卓也
Biogeosciences, 10(6), p.3839 - 3847, 2013/06
被引用回数:24 パーセンタイル:57.49(Ecology)福島第一原子力発電所事故により環境中にさまざまな放射性物質が放出された。事故起因の Iの影響を評価することを目的に事故前後における海水中の
Iの影響を評価することを目的に事故前後における海水中の I濃度を測定した。事故前の
I濃度を測定した。事故前の I濃度の結果から北太平洋の北緯36度から44度における濃度分布は緯度の減少とともに減少している傾向を示した。事故後の海水中の
I濃度の結果から北太平洋の北緯36度から44度における濃度分布は緯度の減少とともに減少している傾向を示した。事故後の海水中の I濃度は最大値で73倍、平均値で約8倍上昇していることが明らかとなった。また鉛直分布の結果から水深1000mまでの事故起因
I濃度は最大値で73倍、平均値で約8倍上昇していることが明らかとなった。また鉛直分布の結果から水深1000mまでの事故起因 Iのインベントリーは(1.8-9.9)
Iのインベントリーは(1.8-9.9) 10
10 atoms/m
atoms/m であった。海水中の
であった。海水中の I測定結果から海産生物摂取による内部被ばく量を見積もったところ、事故起因の
I測定結果から海産生物摂取による内部被ばく量を見積もったところ、事故起因の Iによる被ばく量は極めて小さいと考えられる。
Iによる被ばく量は極めて小さいと考えられる。
 Co in the digestive glands of the common octopus,
Co in the digestive glands of the common octopus, 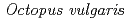 , in the East China Sea
, in the East China Sea森田 貴己*; 乙坂 重嘉; 藤本 賢*; 西内 耕*; 木元 克則*; 山田 東也*; 葛西 広海*; 皆川 昌幸*; 吉田 勝彦*
Marine Pollution Bulletin, 60(8), p.1193 - 1199, 2010/08
被引用回数:3 パーセンタイル:10.2(Environmental Sciences)1989年代から2000年代にかけての2期間(1986年から1989年と1996から2005年)に東シナ海で採取したマダコ(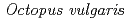 )を採取し、消化腺及び筋肉中の放射性核種濃度を測定した結果、周辺海域のそれに比べてわずかに高い人為起源放射性核種(コバルト60,セシウム137及び銀108m)濃度が検出された。その濃度と濃度比から、1980年代の高濃度は、全球フォールアウトによるものと推定された。コバルト60の濃度(試料採取時に減衰補正)は、1996年から2005年にかけて指数関数的に減少したが、その実効半減期は物理的半減期に比べて短かった。この傾向から、1990年代に見られた高いコバルト60の濃度は、単一の供給源によるもので、かつ、一時的に供給されたものであると推測された。同時期に他の海域で採取されたマダコの分析結果と比較したところ、コバルトの供給源は、日本列島の沿岸ではなく、東シナ海に限定できることが示唆された。
)を採取し、消化腺及び筋肉中の放射性核種濃度を測定した結果、周辺海域のそれに比べてわずかに高い人為起源放射性核種(コバルト60,セシウム137及び銀108m)濃度が検出された。その濃度と濃度比から、1980年代の高濃度は、全球フォールアウトによるものと推定された。コバルト60の濃度(試料採取時に減衰補正)は、1996年から2005年にかけて指数関数的に減少したが、その実効半減期は物理的半減期に比べて短かった。この傾向から、1990年代に見られた高いコバルト60の濃度は、単一の供給源によるもので、かつ、一時的に供給されたものであると推測された。同時期に他の海域で採取されたマダコの分析結果と比較したところ、コバルトの供給源は、日本列島の沿岸ではなく、東シナ海に限定できることが示唆された。
森田 貴己*; 丹羽 健太郎*; 藤本 賢*; 葛西 広海*; 山田 東也*; 西内 耕*; 坂本 竜哉*; 牛堂 和一郎*; 田井野 清也*; 林 芳弘*; et al.
Science of the Total Environment, 408(16), p.3443 - 3447, 2010/06
被引用回数:13 パーセンタイル:32.9(Environmental Sciences)日本沿岸域で採取した褐藻からヨウ素-131( I)が検出された。褐藻は高い濃縮係数によって放射性核種を体内に蓄積することから、放射性ヨウ素の生物指標として広く使われている。測定された褐藻に含まれる
I)が検出された。褐藻は高い濃縮係数によって放射性核種を体内に蓄積することから、放射性ヨウ素の生物指標として広く使われている。測定された褐藻に含まれる Iの比放射能の最大値は0.37
Iの比放射能の最大値は0.37 0.010Bq/kg-wetであった。本研究で採取したすべての褐藻からセシウム-137(
0.010Bq/kg-wetであった。本研究で採取したすべての褐藻からセシウム-137( Cs)も検出された。これらの海藻における
Cs)も検出された。これらの海藻における Iと
Iと Csの比放射能には相関はなかった。
Csの比放射能には相関はなかった。 Csの比放射能は0.0034
Csの比放射能は0.0034 0.00075から0.090
0.00075から0.090 0.014Bq/kg-wetの範囲であった。褐藻中
0.014Bq/kg-wetの範囲であった。褐藻中 Csの低い比放射能と変動幅の少ない濃度から、
Csの低い比放射能と変動幅の少ない濃度から、 Csのソースが過去の核実験であることを示唆している。原子力発電所や核燃料再処理施設は
Csのソースが過去の核実験であることを示唆している。原子力発電所や核燃料再処理施設は Iの汚染源であることは知られているが、
Iの汚染源であることは知られているが、 Iが検出された海域と核関連施設が立地する地域との関連はなかった。
Iが検出された海域と核関連施設が立地する地域との関連はなかった。 Iが検出されたほとんどの海域は多くの人口を抱える大都市近傍であった。
Iが検出されたほとんどの海域は多くの人口を抱える大都市近傍であった。 Iは医療の放射線診断や治療にしばしば用いられる。本研究結果から、著者らは褐藻から検出された
Iは医療の放射線診断や治療にしばしば用いられる。本研究結果から、著者らは褐藻から検出された Iのソースは、原子力発電施設起因ではなく、放射線治療行為によるものであると考えている。
Iのソースは、原子力発電施設起因ではなく、放射線治療行為によるものであると考えている。
鈴木 崇史; 皆川 昌幸*; 甲 昭二; 外川 織彦
第12回AMSシンポジウム報告集, p.69 - 72, 2010/05
原子力利用によって放出された Iは、日本海の海水循環を考察するうえで有効なトレーサーであると考えられる。そこで、日本海における
Iは、日本海の海水循環を考察するうえで有効なトレーサーであると考えられる。そこで、日本海における I濃度の水平及び鉛直分布を明らかにした。表面海水中の濃度レベルは核実験による濃度レベルより高かった。これは欧州及び米国の再処理工場から放出された
I濃度の水平及び鉛直分布を明らかにした。表面海水中の濃度レベルは核実験による濃度レベルより高かった。これは欧州及び米国の再処理工場から放出された Iが飛来してきたものだと考えられる。日本海底層水(JSBW)では人為起源
Iが飛来してきたものだと考えられる。日本海底層水(JSBW)では人為起源 Iが観測された。この観測された人為起源
Iが観測された。この観測された人為起源 Iの濃度レベルからJSBWのturnover timeとpotential formation rateを見積もった。結果はそれぞれ180
Iの濃度レベルからJSBWのturnover timeとpotential formation rateを見積もった。結果はそれぞれ180 210年と(3.9
210年と(3.9 4.6)
4.6) 10
10 m
m /yrであった。また本発表では国際原子力機関海洋環境研究所で行われた海水中の
/yrであった。また本発表では国際原子力機関海洋環境研究所で行われた海水中の I相互比較検定において青森研究開発センターで測定した結果が推奨値の範囲内に入っており、良い精度及び正確さを持って測定したことも併せて報告する。
I相互比較検定において青森研究開発センターで測定した結果が推奨値の範囲内に入っており、良い精度及び正確さを持って測定したことも併せて報告する。
鈴木 崇史; 皆川 昌幸*; 天野 光; 外川 織彦
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 268, p.1229 - 1231, 2010/04
被引用回数:26 パーセンタイル:85.04(Instruments & Instrumentation)ヨウ素129( I)は半減期1570万年の長寿命放射性核種であり、核実験や核燃料再処理工場の稼動により人為起源
I)は半減期1570万年の長寿命放射性核種であり、核実験や核燃料再処理工場の稼動により人為起源 Iが環境中に放出される。六ヶ所村に新たに使用済核燃料再処理工場が定常運転を開始予定であり
Iが環境中に放出される。六ヶ所村に新たに使用済核燃料再処理工場が定常運転を開始予定であり Iの放出が予想される。そこで再処理工場の定常運転前における海水中の
Iの放出が予想される。そこで再処理工場の定常運転前における海水中の Iの分布を把握することは長期的な環境影響評価の観点から重要である。また人為起源
Iの分布を把握することは長期的な環境影響評価の観点から重要である。また人為起源 Iは海水循環のトレーサーとして利用できる可能性がある。そこで本研究では太平洋,日本海における
Iは海水循環のトレーサーとして利用できる可能性がある。そこで本研究では太平洋,日本海における Iの鉛直分布を明らかにした。太平洋及び日本海における
Iの鉛直分布を明らかにした。太平洋及び日本海における Iの濃度は表層及び亜表層で最も高く水深とともに減少した。太平洋においては水深1500m以下において人為起源
Iの濃度は表層及び亜表層で最も高く水深とともに減少した。太平洋においては水深1500m以下において人為起源 Iは観測されなかった。この結果は従来トレーサーとして利用されている
Iは観測されなかった。この結果は従来トレーサーとして利用されている Cや
Cや Csと同様の結果を示した。
Csと同様の結果を示した。 Iは放出源及び放出量がより明確であることや分析に使用する供試量が少ないことから海水循環を解明する有用なトレーサーになり得ると考えられる。また日本海における
Iは放出源及び放出量がより明確であることや分析に使用する供試量が少ないことから海水循環を解明する有用なトレーサーになり得ると考えられる。また日本海における Iの水柱における総量は太平洋に比べて3倍高かった。これは日本海固有の海底地形及び海水循環によるものと考えている。
Iの水柱における総量は太平洋に比べて3倍高かった。これは日本海固有の海底地形及び海水循環によるものと考えている。
 C同位体比からみた日本海における粒子状物質の輸送過程
C同位体比からみた日本海における粒子状物質の輸送過程乙坂 重嘉; 田中 孝幸; 皆川 昌幸*
JAEA-Conf 2010-001, p.113 - 117, 2010/03
日本海東部とそこに流入する河川で採取した粒子試料(懸濁粒子,沈降粒子,堆積物)について、有機物を構成する安定炭素( C)及び放射性炭素(
C)及び放射性炭素( C)の同位体比を測定し、同海域における粒子状物質の動態を議論した。得られた結果から、(1)沈降粒子中の
C)の同位体比を測定し、同海域における粒子状物質の動態を議論した。得られた結果から、(1)沈降粒子中の C同位体比と
C同位体比と C同位体比の関係は、海水柱内での有機物の変質の程度(数日から数年)を示すこと、(2)懸濁物や堆積物中のそれは、海水中での移動時間(数年から数千年)を示すことがわかった。日本列島に近い4観測点の堆積物中の
C同位体比の関係は、海水柱内での有機物の変質の程度(数日から数年)を示すこと、(2)懸濁物や堆積物中のそれは、海水中での移動時間(数年から数千年)を示すことがわかった。日本列島に近い4観測点の堆積物中の C同位体比は、陸棚縁辺(観測点に至近の200m等深線)からの水平距離とともに減少しており、この
C同位体比は、陸棚縁辺(観測点に至近の200m等深線)からの水平距離とともに減少しており、この C同位体比の減少を粒子輸送時の
C同位体比の減少を粒子輸送時の Cの放射性壊変によるものと仮定すると、同海域の底層における沿岸-海盆間での物質の水平輸送速度は約200m/年であると見積もられた。
Cの放射性壊変によるものと仮定すると、同海域の底層における沿岸-海盆間での物質の水平輸送速度は約200m/年であると見積もられた。
 Cの分布と輸送過程
Cの分布と輸送過程乙坂 重嘉; 鈴木 崇史; 田中 孝幸
KURRI-KR-153, p.41 - 46, 2010/03
日本海における現在の人工放射性核種の分布は、特定の原子力施設・事象によって決定付けられたものではなく、グローバルフォールアウト等によって表面に供給された放射性核種が、独自の物質循環機構によって内部に運ばれた結果を示すものであると推測されている。しかしながら、その詳細な移行過程は不明な点が多い。本研究では、空間的に密な放射性炭素の分布から、海水流動に伴う人為起源放射性核種の移行過程を追跡することを目的として、日本海の81観測点において、1,300を超える海水試料中の放射性炭素分析を行った。分析を効率的に進めるため、少量の試料で分析が可能な加速器質量分析法を採用した。得られた結果から、(1)東シナ海からの供給,(2)対馬暖流による表層の南北輸送,(3)北西部海域における深層への輸送、といった移行過程が証明されたばかりでなく、日本海における人為起源放射性炭素量の見積もりが可能となった。
 I及び
I及び Cの鉛直分布
Cの鉛直分布鈴木 崇史; 皆川 昌幸*; 外川 織彦
第11回AMSシンポジウム報告集, p.31 - 34, 2009/01
日本海の東部日本海盆における海水試料中の I及び
I及び Cの濃度を表層から底層まで加速器質量分析装置で測定した。
Cの濃度を表層から底層まで加速器質量分析装置で測定した。 I,
I,  Cともに表層で濃度極大を示し、水深とともに減少していた。底層水中の
Cともに表層で濃度極大を示し、水深とともに減少していた。底層水中の I及び
I及び Cは一定値を示した。2007年7月及び11月に採取した海水中の
Cは一定値を示した。2007年7月及び11月に採取した海水中の I /
I / Iはそれぞれ(7.1
Iはそれぞれ(7.1 0.8)
0.8) 10
10 及び(6.7
及び(6.7 0.3)
0.3) 10
10 であり誤差範囲内で一致した。また2007年7月に同時に採取した海水中の
であり誤差範囲内で一致した。また2007年7月に同時に採取した海水中の
 Cは-58
Cは-58 7‰であった。本研究で得られた底層水中の
7‰であった。本研究で得られた底層水中の I及び
I及び Cから日本海底層水turnover timeを見積もった。
Cから日本海底層水turnover timeを見積もった。 Iの場合、核実験以前の
Iの場合、核実験以前の I/
I/ Iレベルが1.5
Iレベルが1.5 10
10 から約60年間で現在のレベルに到達したことから見積もった。
から約60年間で現在のレベルに到達したことから見積もった。 Cの場合Gamo et al. 1983で観測された東部日本海盆における
Cの場合Gamo et al. 1983で観測された東部日本海盆における
 C値-80
C値-80 8‰から30年間で
8‰から30年間で
 Cが22‰増加したことから推定した。
Cが22‰増加したことから推定した。 I及び
I及び Cから見積もられたturnover timeはそれぞれ300年と270年であった。
Cから見積もられたturnover timeはそれぞれ300年と270年であった。
荒巻 能史*; 外川 織彦; 乙坂 重嘉; 鈴木 崇史; 天野 光; 田中 孝幸; 千手 智晴*; 皆川 昌幸*
JAEA-Conf 2008-005, p.149 - 152, 2008/03
原子力機構では、1990年代後半より日本海全域における人工放射性核種濃度の現状把握、及び日本海深層の物質循環について観測研究を実施してきた。本報告では、これらの観測によって得られた、海水流動のトレーサとして有効な放射性炭素( C)の広範な分布をもとに、深層水の特性やその循環について議論した。1999
C)の広範な分布をもとに、深層水の特性やその循環について議論した。1999 2002年及び2005年に実施した調査で得られた海水試料中の
2002年及び2005年に実施した調査で得られた海水試料中の Cを、むつ事務所の加速器質量分析装置で測定した。その結果、各海域の
Cを、むつ事務所の加速器質量分析装置で測定した。その結果、各海域の
 Cは表層の+70‰程度から深度とともに指数関数的に減少する傾向にあるが、日本海盆などの水深2000m以深では-65‰前後でほぼ一定の値となった。また、日本海盆西部域やウツリョウ海盆の底層水における
Cは表層の+70‰程度から深度とともに指数関数的に減少する傾向にあるが、日本海盆などの水深2000m以深では-65‰前後でほぼ一定の値となった。また、日本海盆西部域やウツリョウ海盆の底層水における
 Cにばらつきが顕著であるのに対して、日本海盆東部域では誤差範囲内で一定の値を示した。以上のように、日本海の各海域における底層水の特性を明らかにすることができ、その要因や底層水の循環について考察した。
Cにばらつきが顕著であるのに対して、日本海盆東部域では誤差範囲内で一定の値を示した。以上のように、日本海の各海域における底層水の特性を明らかにすることができ、その要因や底層水の循環について考察した。
高田 兵衛*; 久万 健志*; 磯田 豊*; 乙坂 重嘉; 千手 智晴*; 皆川 昌幸*
Geophysical Research Letters, 35(2), p.L02606_1 - L02606_5, 2008/01
被引用回数:19 パーセンタイル:44.13(Geosciences, Multidisciplinary)日本海の2つの海盆(大和海盆及び日本海盆)で採取した海水中の鉄(溶存鉄と可溶性鉄)濃度から、両海盆での鉄の挙動について考察した。孔径0.22 mのフィルターで濾過し、緩衝液でpH=3.2に調整した海水に含まれる鉄を溶存鉄、濾過せずにpH調整のみを行った海水に含まれる鉄を可溶性鉄とした。表層(0
mのフィルターで濾過し、緩衝液でpH=3.2に調整した海水に含まれる鉄を溶存鉄、濾過せずにpH調整のみを行った海水に含まれる鉄を可溶性鉄とした。表層(0 200m深)における可溶性鉄存在量は、いずれの海域でも300
200m深)における可溶性鉄存在量は、いずれの海域でも300 350
350 mol m
mol m で、北太平洋の外洋域に比べて5
で、北太平洋の外洋域に比べて5 9倍大きく、アジア大陸から日本海への大気経由での物質輸送が鉄の存在量に大きく影響していると推測された。日本海における溶存鉄濃度は、水深1
9倍大きく、アジア大陸から日本海への大気経由での物質輸送が鉄の存在量に大きく影響していると推測された。日本海における溶存鉄濃度は、水深1 2kmで極大を示した。この結果は、表層で生物に取り込まれた鉄が、中・深層で分解され滞留したためであると考えられる。鉄は、海洋における生物生産を制限する重要な因子であることが指摘されているが、日本海における鉄濃度分布から、海洋における鉄の供給源と挙動について理解することが可能となった。
2kmで極大を示した。この結果は、表層で生物に取り込まれた鉄が、中・深層で分解され滞留したためであると考えられる。鉄は、海洋における生物生産を制限する重要な因子であることが指摘されているが、日本海における鉄濃度分布から、海洋における鉄の供給源と挙動について理解することが可能となった。
鈴木 崇史; 皆川 昌幸*; 天野 光; 外川 織彦
第10回AMSシンポジウム報告集, p.147 - 150, 2008/00
ヨウ素129は半減期1570万年の長寿命放射性核種である。大気核実験や核燃料再処理工場の稼動により環境中に Iが放出されるため、環境中での
Iが放出されるため、環境中での Iの移行挙動が注目されている。そこで本研究では海水中の
Iの移行挙動が注目されている。そこで本研究では海水中の I濃度を測定することにより、海水中の
I濃度を測定することにより、海水中の Iの移行挙動を考察した。海水試料は太平洋の1地点(釧路沖)と日本海の2地点(日本海盆及び大和海盆)で採取した。試料中の
Iの移行挙動を考察した。海水試料は太平洋の1地点(釧路沖)と日本海の2地点(日本海盆及び大和海盆)で採取した。試料中の I/
I/ Iは原子力機構むつ事務所のAMSで測定した。表面海水中(水深5m)の
Iは原子力機構むつ事務所のAMSで測定した。表面海水中(水深5m)の I/
I/ Iは釧路沖、日本海盆及び大和海盆でそれぞれ(7.1
Iは釧路沖、日本海盆及び大和海盆でそれぞれ(7.1 0.5)
0.5) 10
10 , (5.8
, (5.8 0.2)
0.2) 10
10 及び(4.6
及び(4.6 0.6)
0.6) 10
10 であった。釧路沖の
であった。釧路沖の I鉛直分布は水深とともに減少した。水深1500mから5000mまでの
I鉛直分布は水深とともに減少した。水深1500mから5000mまでの I濃度は一定となり、
I濃度は一定となり、 I/
I/ I=(1.4
I=(1.4 0.6)
0.6) 10
10 を得た。人為起源
を得た。人為起源 Iを含まない天然レベルの
Iを含まない天然レベルの I/
I/ Iが(1.5
Iが(1.5 0.15)
0.15) 10
10 であることから太平洋の1500m深まで人為起源の
であることから太平洋の1500m深まで人為起源の Iが沈み込んでいることがわかった。一方、日本海の日本海盆と大和海盆では
Iが沈み込んでいることがわかった。一方、日本海の日本海盆と大和海盆では I濃度は太平洋と同様に水深とともに減少し、2000m以深で一定値となり、その
I濃度は太平洋と同様に水深とともに減少し、2000m以深で一定値となり、その I/
I/ Iは日本海盆と大和海盆でそれぞれ(8.3
Iは日本海盆と大和海盆でそれぞれ(8.3 0.6)
0.6) 10
10 及び(9.8
及び(9.8 0.8)
0.8) 10
10 であった。天然レベルの
であった。天然レベルの I/
I/ I値から考えると、人為起源
I値から考えると、人為起源 Iが日本海の深部まで沈み込んでいるためだと考えられる。
Iが日本海の深部まで沈み込んでいるためだと考えられる。
乙坂 重嘉; 外川 織彦; 田中 孝幸; 天野 光; 皆川 昌幸*
no journal, ,
日本海深海域における粒子状物質の生物地球化学循環を明らかにするため、西部日本海盆(WJB),東部日本海盆(EJB)及び大和海盆(YB)の3海域で得られた沈降粒子中の鉛-210(Pb-210)濃度と有機態放射性炭素(C-14)同位体比を測定結果から、粒子の輸送過程とその時間スケールについて検討した。水深1km層における沈降粒子中のデルタ14C値は、-13 22パーミルで、海域による差は見られなかった。底層(海底上200m)で得られた沈降粒子中のデルタ14C値は、YBでは水深1km層のそれと同程度であったが、WJB及びEJBでは、浅層の値に比べて55パーミル程度低かった。このことから、日本海北部(WJB and EJB)の深海域では、南東部(YB)に比べて長い時間スケールでのPOC循環を持つことが示唆された。海水柱内の鉛-210(Pb-210)の収支をWJBとEJB間で比較した結果、WJBに供給されるPb-210の60%は東部に輸送されていると見積もられた。
22パーミルで、海域による差は見られなかった。底層(海底上200m)で得られた沈降粒子中のデルタ14C値は、YBでは水深1km層のそれと同程度であったが、WJB及びEJBでは、浅層の値に比べて55パーミル程度低かった。このことから、日本海北部(WJB and EJB)の深海域では、南東部(YB)に比べて長い時間スケールでのPOC循環を持つことが示唆された。海水柱内の鉛-210(Pb-210)の収支をWJBとEJB間で比較した結果、WJBに供給されるPb-210の60%は東部に輸送されていると見積もられた。
乙坂 重嘉; 皆川 昌幸*; 乗木 新一郎*
no journal, ,
日本海におけるセジメントトラップ実験を行うことにより、海洋全体における粒子輸送過程の傾向や、全球的な環境変動に対する深海への粒子輸送の応答についての情報を効率的に得ることができる。本講演では、原子力機構,北海道大学,中央水研が1999年代後半から2000年代前半にかけて日本海で行ったセジメントトラップ実験の成果を紹介する。日本海における全粒子束は東部に比べて栄養塩の表層への供給が活発な北西部で大きかった。希土類元素等を指標とすることにより、日本海への陸起源粒子の供給経路を3つに分類できた。鉛の放射性同位体であるPb-210の収支から、西部日本海盆の深層に鉛直的に運ばれた粒子状物質の約6割が日本海盆深層を通って東方に運ばれていると推測された。日本海のような「モデル海域」で明らかにされる粒子の循環像と、1980年代より西部北太平洋域で連続的に行われている連続観測の結果を組合せることにより、より包括的な物質循環像を明らかにすることが期待される。
乙坂 重嘉; 天野 光; 田中 孝幸; 外川 織彦; 乗木 新一郎*; 蒲 正人*; 皆川 昌幸*
no journal, ,
日本海深海域における粒子状親生物元素の循環を明らかにするため、1999年代後半から2000年代前半にかけて日本海の3海域(北東部,北西部,南東部)で実施したセジメントトラップ実験で得た沈降粒子と、2海域(北東部,南東部)での現場濾過実験で得た懸濁粒子中の有機態放射性炭素(C-14)同位体比分析を行い、その時空間変化から、親生物元素の粒子化や海水中での粒子の輸送過程について解析した。水深1km層における沈降粒子中のC-14同位体比には、その変動範囲に大きな海域差が見られなかった。深層(海底の500m上)で得られた沈降粒子中のC-14同位体比は、日本海南東部では水深1km層における値と比べて大きな差が見られなかったが、その一方で北東部及び北西部では、上層に比べて有意に小さかった。これらの結果から、日本海北部では、南部に比べて時空間的に大きな粒子状有機物の循環・蓄積機構が働いているか、有機物の供給源・供給過程が南北で大きく異なることが示唆された。
荒巻 能史*; 外川 織彦; 乙坂 重嘉; 鈴木 崇史; 千手 智晴*; 皆川 昌幸*
no journal, ,
原子力機構では、1990年代後半より日本海全域における人工放射性核種濃度の現状把握、及び日本海深層の物質循環について観測研究を実施してきた。本報告では、これらの観測によって得られた海水流動のトレーサとして有効な放射性炭素( C)の広範な分布をもとに、深層水の特性やその循環について議論した。1999
C)の広範な分布をもとに、深層水の特性やその循環について議論した。1999 2002年及び2005年に実施した調査で得られた海水試料中の
2002年及び2005年に実施した調査で得られた海水試料中の Cを、むつ事業所の加速器質量分析装置で測定した。その結果、各海域の
Cを、むつ事業所の加速器質量分析装置で測定した。その結果、各海域の
 Cは表層の+70‰程度から深度とともに指数関数的に減少する傾向にあるが、日本海盆及び大和海盆の水深2000m以深では-50
Cは表層の+70‰程度から深度とともに指数関数的に減少する傾向にあるが、日本海盆及び大和海盆の水深2000m以深では-50 -70‰でほぼ一定の値となった。また、大和海盆と日本海盆西部の底層水における
-70‰でほぼ一定の値となった。また、大和海盆と日本海盆西部の底層水における
 Cにばらつきが顕著であるのに対して、日本海盆東部では水深2500m以深において、誤差範囲内で一定の値を示した。以上のように、日本海の各海域における底層水の特性を明らかにすることができた。
Cにばらつきが顕著であるのに対して、日本海盆東部では水深2500m以深において、誤差範囲内で一定の値を示した。以上のように、日本海の各海域における底層水の特性を明らかにすることができた。
鈴木 崇史; 天野 光; 外川 織彦; 皆川 昌幸*
no journal, ,
日本海における大和海盆及び富山湾のヨウ素129の鉛直分布を加速器質量分析装置を用いることにより明らかにした。濃度は表面で高く水深1000m付近まで減少し、それ以深ではほぼ一定となった。天然起源のヨウ素129は一定値(0.04 10
10 atoms/L)になっていると考えられる。日本海固有水の占める水深1000mから3000mまでもこの値よりも有意に大きい。日本海固有水が入れ替わるのに約100年かかることを考慮すると、ヨウ素の移行挙動の一部には早い鉛直方向の移行過程が存在するのではないかと考えられる。これには、冬季に表層水の深層への貫入、もしくはエアロゾルや海藻などの粒子に吸着もしくは取り込まれたヨウ素が海水中を沈降し深層中で溶解する過程が考えられる。
atoms/L)になっていると考えられる。日本海固有水の占める水深1000mから3000mまでもこの値よりも有意に大きい。日本海固有水が入れ替わるのに約100年かかることを考慮すると、ヨウ素の移行挙動の一部には早い鉛直方向の移行過程が存在するのではないかと考えられる。これには、冬季に表層水の深層への貫入、もしくはエアロゾルや海藻などの粒子に吸着もしくは取り込まれたヨウ素が海水中を沈降し深層中で溶解する過程が考えられる。
乙坂 重嘉; 田中 孝幸; 天野 光; 外川 織彦; 乗木 新一郎*; 皆川 昌幸*
no journal, ,
海洋における粒子状有機物(POM: Particulate Organic Matter)中の放射性炭素(C-14)同位体比から得られるPOMの「見かけの年齢」は、POMの輸送過程を追跡するための指標として有効である。しかしながら、POM中C-14の同位体比は、海洋表層でのPOM生産時からの経過時間ばかりではなく、海底や陸域からのPOMの供給や、海水中に溶存する有機物の粒子化の程度をも反映して変化することが指摘されている。そこで本講演では、北海道西方沖,日高沖の2海域と、その周辺地域で得られたPOM試料の分析結果から、POM中の「見かけの年齢」を変化させる因子について議論する。いずれの海域でも、デルタC-14値は深さとともに減少し、試料を採取した水深から海底までの距離と、デルタC-14値との間には、有意な関係は見られなかった。この結果から、海水柱内には「古い」POMが確かに存在するが、その「古さ」は海底からの物質供給のみでは決定付けられないことがわかった。沈降POMと懸濁POMではデルタC-14値とデルタC-13値(安定炭素同位体比)との関係が異なり、懸濁POMは微生物等による海水中での再食の結果を、沈降POMは陸起源POMの混入をそれぞれ反映することが示唆された。
乙坂 重嘉; 奥 俊輔*; 南 秀樹*; 皆川 昌幸*; 乗木 新一郎*
no journal, ,
日本海における深層循環の経年変化は全球的な温暖化と密接に関係していることが示唆されている。一方で、粒子状物質の鉛直輸送は、海洋における物質循環を議論するうえで不可欠な過程であるにもかかわらず、日本海での沈降粒子について、その元素組成の経年変化を論じた研究は皆無である。本研究では、1984年に日本海東部で実施したセジメントトラップ実験の結果を、1999年から2001年にかけて同海域で行った観測結果と比較することにより、物質循環の指標となる10元素について、沈降粒子の元素組成の経年変化を解析した。結果として、(1)生物起源粒子の特徴の変化に比べ、陸起源成分の組成の変化がより顕著であること,(2)陸起源粒子のうち、アジア大陸起源粒子の構成比が減少した可能性があること,(3)沿岸域から海盆内部への粒子輸送量が減少したこと、及び沈降粒子による人為起源微量元素の輸送量には有意な増加がないことが示唆された。
鈴木 崇史; 皆川 昌幸*; 外川 織彦
no journal, ,
海洋環境における Iの化学トレーサーとしての可能性を検討するために、西部北太平洋及び東部日本海盆における海水中の
Iの化学トレーサーとしての可能性を検討するために、西部北太平洋及び東部日本海盆における海水中の I/
I/ Iを測定した。両観測点における
Iを測定した。両観測点における I/
I/ Iの鉛直分布はともに表層が最も高く、西部北太平洋では1500m以深で、東部日本海盆では2500m以深(底層水)で一定値を示した。その
Iの鉛直分布はともに表層が最も高く、西部北太平洋では1500m以深で、東部日本海盆では2500m以深(底層水)で一定値を示した。その I/
I/ I値はそれぞれ(1.5
I値はそれぞれ(1.5 0.4)
0.4) 10
10 及び(7.1
及び(7.1 0.8)
0.8) 10
10 であった。西部北太平洋の水深1500m以深では核実験起源のトレーサーが貫入していないことから1500m以深の一定値は海洋環境における天然レベルの
であった。西部北太平洋の水深1500m以深では核実験起源のトレーサーが貫入していないことから1500m以深の一定値は海洋環境における天然レベルの I/
I/ Iを示しているものと考えられる。東部日本海盆底層水の
Iを示しているものと考えられる。東部日本海盆底層水の I/
I/ Iは天然レベルの
Iは天然レベルの I/
I/ Iより高かった。この濃度差から日本海底層水のturnover timeを求めた。
Iより高かった。この濃度差から日本海底層水のturnover timeを求めた。 Iから求められたturnover timeは約300年であった。他の化学トレーサーから推定された日本海のturnover timeは100から500年程度だと報告されており、
Iから求められたturnover timeは約300年であった。他の化学トレーサーから推定された日本海のturnover timeは100から500年程度だと報告されており、 Iからも同程度の値を得たこから
Iからも同程度の値を得たこから Iもトレーサーとして有用であると考えられる。
Iもトレーサーとして有用であると考えられる。
鈴木 崇史; 皆川 昌幸*; 外川 織彦
no journal, ,
日本海は水温の上昇,溶存酸素濃度の低下が観測され、地球温暖化に対して影響を受けやすい海域であることが知られている。そこで、日本海の海水循環過程を明らかにするために、海水中の Iを測定した。海水試料は中央水産研究所所有の蒼鷹丸及び北海道大学所有のおしょろ丸の航海で採取した。両航海で得られた日本海底層水中の
Iを測定した。海水試料は中央水産研究所所有の蒼鷹丸及び北海道大学所有のおしょろ丸の航海で採取した。両航海で得られた日本海底層水中の I/
I/ Iはそれぞれ(7.1
Iはそれぞれ(7.1 0.8)
0.8) 10
10 及び(6.7
及び(6.7 0.3)
0.3) 10
10 であった。天然レベルの
であった。天然レベルの I/
I/ I=1.5
I=1.5 10
10 から約60年で現在の濃度レベルになったことを利用し、日本海底層水のturnover timeを見積もった。見積もられたturnover timeは180-210年であった。他のトレーサーから見積もられているturnover timeは100-500年程度であり、
から約60年で現在の濃度レベルになったことを利用し、日本海底層水のturnover timeを見積もった。見積もられたturnover timeは180-210年であった。他のトレーサーから見積もられているturnover timeは100-500年程度であり、 Iを利用することにより、詳細なturnover timeを求めることができた。
Iを利用することにより、詳細なturnover timeを求めることができた。